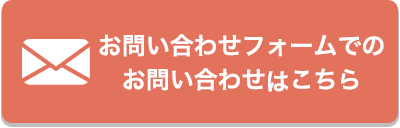帝王切開術後に肺血栓塞栓症を発症し死亡した事例で、約1億3000万円の損害賠償請求を認めたケース
宮崎地裁判決 平成30年9月12日
概要
妊婦であるAが子を帝王切開術で出産しましたが、術後に深部静脈血栓症を発症し、その症状が見落とされ、その結果生じた肺血栓塞栓症により死亡した事案です。
裁判では医師による鑑定が行われ、術後3日目に左下肢の浮腫が確認できた時点で深部静脈血栓症を疑うべきであるという意見が出されました。また深部静脈血栓症の症状として、浮腫・腫脹、疼痛、熱感・色調変更などがありますが、そのうち浮腫・腫脹の症状だけでも深部静脈血栓症を疑うべきという意見も出されました。
裁判所は、術後3日目の朝に左足の浮腫を確認した時点で、深部静脈血栓症を疑い必要な措置をとるべき注意義務があったと認定し、そのような措置を怠った結果、肺血栓塞栓症を発症し死亡したとして、被告医師の責任を認め、約1億3000万円の賠償請求を認めました。
事案
亡くなったAは、被告医師の勤務するクリニックにおいて帝王切開で子を出産し、術後、下肢深部静脈血栓症予防のために弾性ストッキングを着用していました。Aは手術の2日後までベッド上で過ごしていましたが、同日午後3時から歩行を開始しました。手術3日後の午前6時50分に、Aの左足に浮腫が生じているのが確認されました。同日午後11時33分頃にAが携帯電話で撮影した左足は、右足と比べると腫脹しており、赤みを帯びていました。手術4日後の午前0時15分頃、クリニック2階のナースステーション前でAが倒れているところを発見されました。被告である医師Yが駆け付けたところ、Aは「気分が悪い」と大きなあえぎ呼吸をする状態で、もがき苦しんでいる様子でした。同日午前0時29分頃、Aの意識レベルが低下し、呼びかけにも反応せず、痛覚もなかったため、医師Yは、心臓マッサージ及び人工呼吸を開始しました。その後、総合病院に搬送されましたが、Aは蘇生することなく、同日午前2時14分、死亡が確認されました。その後、剖検が行われ、Aの死因につき、左外腸骨静脈に発生した血栓が遊離して肺血栓塞栓症を発症したことによるものと診断されました。
判決
手術3日後の午前6時50分の時点において左下肢の浮腫を確認しており、これは深部静脈血栓症の発症を疑うべき重要な所見であったといえる。そして、左下肢の浮腫の他に熱感、疼痛及び色調変化など深部静脈血栓症を疑わせる所見が確認されなかったとしても、このことから直ちに深部静脈血栓症の可能性を除外することはできない。
手術3日後の午前6時50分頃の時点において、被告医師は深部静脈血栓症の発症を疑った上で、必要な措置をとるべき注意義務があったというべきである。本件クリニックの設備では、深部静脈血栓症の確定診断をすることができなかったと認められ、被告医師は、深部静脈血栓症を発症している可能性があるAについて、上記の必要な措置として、高次医療機関に診断、治療を委ねる他に方法はなかったというべきである。したがって、被告医師は、手術3日後の午前6時50分頃の時点で、Aにつき、深部静脈血栓症の発症を疑い、高次医療機関に転院させるべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠ったものと認められる。
Aは、手術4日後の午前0時15分頃、本件クリニックの2階廊下で倒れているところを発見されたのであるから、Aが致死性の重篤な肺血栓塞栓症を発症したのは、その直前であり、それまでは無症候性の肺血栓塞栓症を発症していた可能性があるにとどまるものと認められる。そして、Aは、手術2日後の午後2時頃に導尿用のバルーンカテーテルを抜去されて以降は、少なくとも、トイレに行く際は起立して歩行をしていたと考えられ、また、授乳の際や子の様子を確認する際に起立して歩行するという動作があったものと考えられる。
他方、被告医師が前記の注意義務を尽くしていた場合、Aは、高次医療機関に転送されることになるが、血栓が遊離して肺血栓塞栓症を発症する危険性を踏まえて、転送の際は、できる限り身体を安静にして、転送がされたものと考えられる。そして、深部静脈血栓症から肺血栓塞栓症を合併した場合の危険性に鑑みれば、同日中の可能な限り早期の段階で診断、治療がされたものと考えられる。上記診断及び治療の内容については、基本的には、平成21年版静脈血栓塞栓症ガイドラインに則った措置がされたと考えられ、具体的には、確定診断のための画像検査(静脈エコー、造影CT撮影等)、静脈造影検査等を実施し、その結果深部静脈血栓症であると確定診断し、薬物療法(抗凝固療法、血栓溶解療法)等の病態に応じた治療がされることになったと想定される。
Aは、被告医師の前記の注意義務違反の時点から17時間以上もの間、深部静脈血栓症の可能性が認識されることなく、かつその治療がされることもなく一定程度起立及び歩行をした状態であったにもかかわらず、致死性の肺血栓塞栓症を発症することはなかったのであるから、被告医師が前記の注意義務を尽くしていた場合には、Aは、できる限り身体を安静にして高次医療機関への転送がされ、Aが現実に急変を生じた時刻よりも相当早期の段階で、ショック状態に至る前に、抗凝固療法及び血栓溶解療法等の治療が開始されたと考えるのが合理的である。そして、平成21年版静脈血栓塞栓症ガイドラインにおいて示された前記の死亡率に関するデータに鑑みれば、上記のような段階で治療が開始されれば、致死性の肺血栓塞栓症を発症してショック状態に至る前に治療効果が現れて、Aが死亡に至らなかった可能性は高いと考えられる。また、仮に、診断途中又は治療途中で致死性の肺血栓塞栓症を発症したとしても、診断又は治療に当たっている医師としてはそのことを十分に想定しているはずであるから、速やかに外科的治療等をも含む適切な対処をするはずであって、なおAを救命できた可能性が一定程度認められる。以上を踏まえれば、被告医師が手術3日後の午前6時50分頃の時点でAにつき、深部静脈血栓症の発症を疑い、高次医療機関に転院させていれば、Aがその死亡時点においてなお生存していたであろうことを是認し得る高度の蓋然性が認められるというべきである。
弁護士のコメント
肺血栓塞栓症とは、肺動脈に血栓がつまり、呼吸苦、胸痛、血痰、ショックなどを起こす病気で、時に死に至ることもあります。深部静脈血栓症は、主に下肢の深い部分の静脈に血栓を生じる病気で、その血栓が遊離して肺動脈に流れ込むと、肺血栓塞栓症を引き起こすことがあります。そのため、下肢深部静脈血栓症が見つかった場合、血栓を溶かすために抗凝固療法が行われることがあります。ただし、膝関節より末梢の深部静脈血栓の場合は、それより中枢側の血栓と比べ肺血栓塞栓症を発症する危険性が低く、抗凝固療法が行われないこともあります。
下肢深部静脈血栓症の症状は、下肢の腫脹・疼痛・発赤などで、下肢の片側に症状が出ることが多いです。ただし、片側下肢に浮腫が生じる疾患は下肢深部静脈血栓症だけではないため、その症状だけで下肢深部静脈血栓症を疑うべきと判断されることはないかもしれません。本件では片側の下肢浮腫のみならず、産後、術後という深部静脈血栓症の危険因子もあったことから、下肢静脈血栓症を疑って精査すべきであったと判断したのではないかと考えられます。