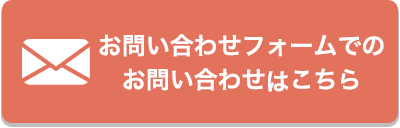放射線科の急性障害から晩期障害に至ったケースについて、医師の責任を認めなかった。
東京高裁 平成元年12月25日
このケースは、小児の再発性未分化胚細胞腫に対する放射線治療中に、急性障害と思われる腹痛・下痢が生じたが、治療の必要性があるとして治療を継続されて不可逆な晩期障害に至っている。判決では、治療の必要性を重視して医師の責任を認めなかった。
放射線治療は、年々増加傾向にあり、急性障害、晩期障害での紛争も増加することが考えられる。このケースでは、治療の必要性が高く、急性障害と晩期障害の関係が不明確で、晩期障害を避けることができたか、という点において医師の責任を認めにくかったケースと考えられる。一方、放射線治療では、照射量や、照射部位などを治療前の綿密な計画に沿って決めていくため、計画の段階で誤りがあり、その結果として障害が生じた場合には医師の責任が認められる。例えば、横浜地裁 平成13年10月31日 判タ1127号212頁では、脳幹部への放射線治療の重複のため、脳幹の耐容線量を超えたケースで、最大耐容線量を越える照射は極めて危険な処置であり一般的には許容できない、として患者の生命の危険を及ぼすような危険な治療が行われたことについて、医師の過失を認めている。当然の判決といえる。